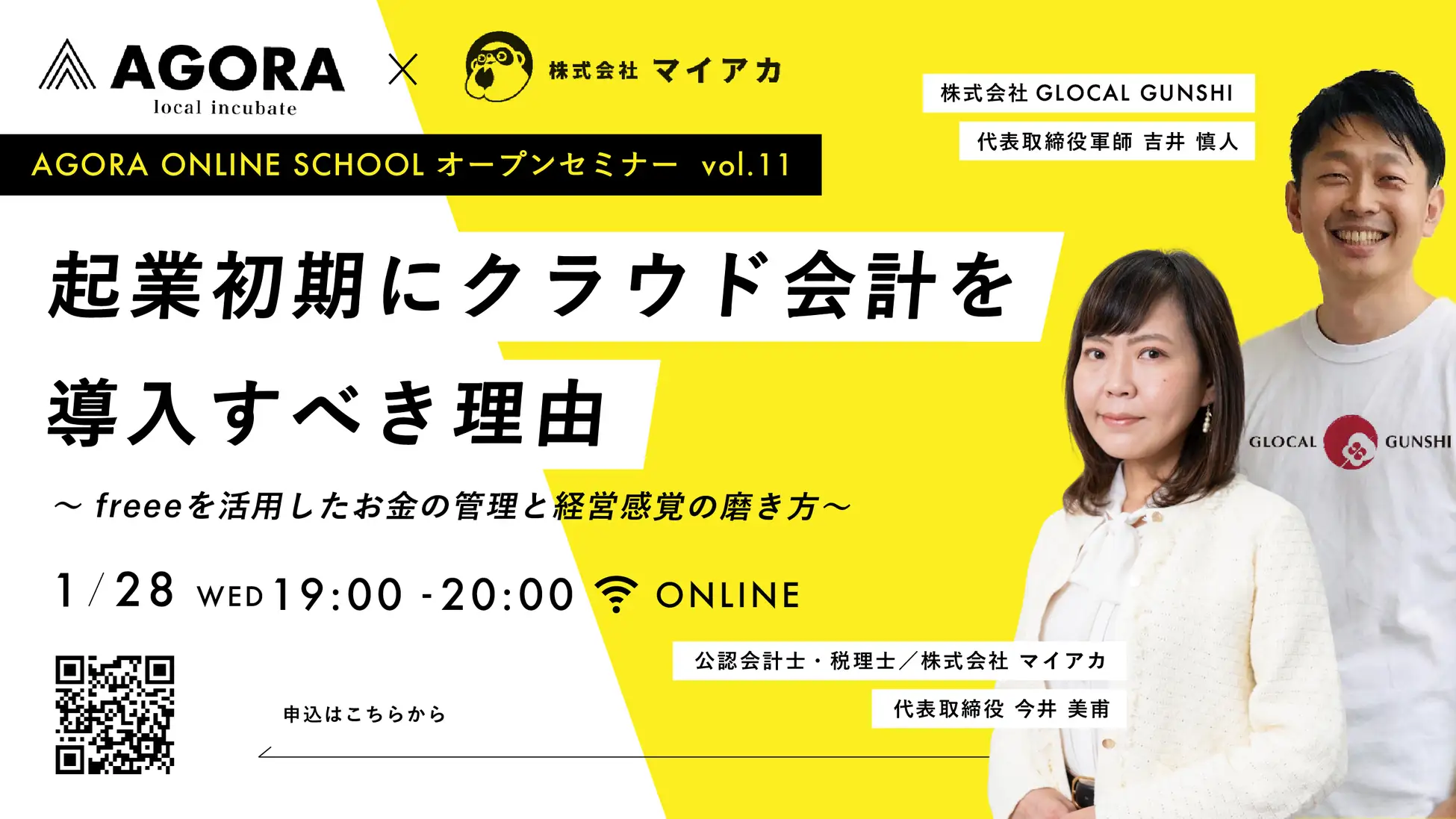論文式試験、おつかれさまでした!
ナレッジ公認会計士日常
9月になりました。まだ猛暑の残る中皆様体調などは崩さずにお過ごしでしょうか。ちょうど先週、公認会計士試験の論文式試験が実施されました。受験された方、本当にお疲れさまでした。3日間を戦い抜いただけ立派なことだと思います。私は論文式試験の当日、始発で会場に行って、3時間くらい朝勉強して試験会場に行きました。今考えればやりすぎ感がありましたが、合格した後はそんなエピソードも思い出になります。
私も、監査論の講師としてすぐに問題に目を通してみましたが、パット見「易しいな・・・?」と思いました。それを弊社の従業員に伝えたところ、先生だからどれをみても易しいのでは?といわれました笑。そして令和7年の論文式試験を改めて確りとみてみましたが、第一問はとても典型的で解きやすいです。ただ、第二問はグループ監査の事例問題なので受験生は取っ付きにくい論点だと思いました。実務を行っていると(特にインチャージなどを経験していると)すっと出てくるような論点なのですが、もちろん受験生におかれましては実務を行ったことがない方がほとんどであるため、ファンタジー要素が強い範囲かなと思います。今年の論文式試験から思うことは、基本的な論点を正確に吐き出せるか、また法令基準集の該当部分に素早くたどり着けるか、だと思います。書いていて、毎年の試験に言えることであり、また現場においてもそういった対応が要求されるな、と思いました。
私はたまに弊社の会計士を目指す職員には、昔こんな仕事をしたというエピソード話をします。監査法人に入所してすぐは、監査手続である確認、証憑突合などを実施すると思います。もう監査論が生かせる部分ですよね。特に私は、スタッフ時代に意識してほしい重要なこととして、証憑突合を挙げています。領収書や請求書は、私に語り掛けてくるんです。この会社はこの時にこんなビジネスをしていますと。だから、証憑突合を単なる事務処理と考えず、重要な手続と考えて、ひとつひとつの監査手続は意味があると思ってやってください、と。私の個人的な考え方かもしれませんが、領収書や請求書は情報の宝庫です。そこから齎される情報が整合性を立証し、また不整合の発見を促します。特に、スタッフ時代はこんなことはつまらない、と思いがちですが、必ずその後のキャリアや監査人としての判断に役に立ちますので、軽視せずに取り組んでもらえたら良いなと考えています。
論文式試験の先には、合格があり、いよいよ実務家としての公認会計士への一歩が始まります。私は、この仕事をしていることが本当に楽しく、色んなところで「生まれ変わっても公認会計士!」と言っているくらいなので、受かった後の世界を楽しみに日々勉強や自己研鑽に励んでほしいと考えています。